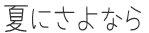黄瀬の涙をが見たあの日から、あっという間に時間が過ぎていった。濃厚で、濃密な毎日が。
IH予選が始まり、新協学園戦、実善高校戦、金賀高校戦、明常高校戦と白稜高校戦を終え、準決勝へ進出を決めた。
やはり誠凛は強い。
油断などしていないが、皆どこか期待があったように思う。 雲を掴むような感覚だったそれが、雲の感触が少しづつ手に伝わってくるような感じ。 もしかしたら、もしかしたら。
けれどそこからは今までと明らかに違った。 それが、全国クラス。 古武術を取り入れた独自のスタイルをもつ正邦高校戦に辛勝、同日の連戦で、本当に苦しかった秀徳高校戦。 そして、決勝リーグへ。
決勝リーグ初戦、桐皇学園にダブルスコアで負け、残りも、全て ――― 。
あれだけ頑張っても手に入らなかった全国への切符。 懸命に励んでもどこか気持ちが入らずにいた。 そんな誠凛メンバーに掲げられたのが、ウィンターカップという新たな目標だった。
この誠凛バスケ部を作った木吉の復帰も皆のモチベーションを上げただろう。
新たな目標に気持ちを切り替え、この夏、WCへ向けての合宿が行われた。
秀徳とまさかの遭遇をした合宿も必死に乗り越え、その最終日。 この合宿が行われたのはIH開催都市。 元々その為にこの地を選んだのかどうかは定かではないけれど、 誠凛メンバーはIH会場へ足を運ぶ事となった。
今日の試合は、海常対桐皇。
黄瀬を見るのは、久々だった。
IH予選の秀徳戦の帰り、雨宿りと休憩で入ったお好み焼き屋で偶然黄瀬と鉢合わせたけれど、 席が離れていた事もあり、会話らしい会話は交わしていない。
帰りに、少し寂しそうな笑顔で、「もうカッコ悪いところは見せないっスよ」 と、言われただけだ。 そして黄瀬は、の言葉も聞かずに去ってしまった。
中学時代、いくら1on1で青峰に負けてもいつもどこか自信が滲んでいた。 そんな黄瀬の、弱々しい表情。 もしかしたら店内での席も、意図的に離れたのかも知れない。 今までだったら、強引にでもの隣に陣取っていただろうから。
それから、黄瀬の事が頭から離れない。
正確には、練習試合のあの日からずっと気になっていたのだが、それよりも、もっと。
「…ふへー!!ノド乾いた!!」
「なんだよコガ、いきなり」
「だってなんかキンチョー感すげーしさー、オレらすげー奴らとやってたんだなーみたいな」
「ほぼマグレ勝ちと惨敗だけどな」
海常高校 対 桐皇学園戦の幕は切って落とされ、既に第2Qが終了した。 試合のちょうど真ん中の、10分のインターバル。
喉が渇いたという小金井を日向は軽くあしらったが、えてして的を射ている。 その会場内の熱気は、夏だから、というだけでは決してない。
IHなだけあり、両校ともスタメン全員レベルが高い。 けれど会場にいる誰しもが注目しているのはやはり青峰と黄瀬で、 二人のプレイは一瞬たりとも目が離せず、観ている者の呼吸すら忘れさせた。
「確かに飲み物ほしいわね」
カントクの一言への兄テツヤが 「なんか買ってきましょうか?」 と、ぽろりと聞くと、 全員からドリンクのリクエストが殺到した。 結局1年全員で買出しへ行く事となりも一緒に席を立ったが、ほぼ無意識の状態で、 ただテツヤの後に付いて行っただけだった。
小さい頃からのクセのようなもので、何も考えていなくても体はテツヤの後を追う。 否、本当は何も考えていない訳ではない。 頭がいっぱいで、他の事が考えられなくなっていた。
試合中、はビデオをまわし、スコアもつけてはいたが、その内容も全く頭に入って来なかった。
目は、黄瀬ばかりを追っていた。
青峰と対峙する黄瀬は、今までに見た事のない目をしていた。 誠凛との練習試合の時に火神へ向けたそれともまた違う。 恐怖すら覚えそうな、ピリピリとした真剣さ。
今まで一回も勝った事のない、もしかしたら勝てなくて良いとさえ思っていたかもしれない青峰に、 黄瀬が本気で勝とうとしている事が痛い程に伝わってきた。
黄瀬くんに、勝って欲しい。
青峰も黄瀬も、どちらも仲間だった。
でもは今、黄瀬に勝って欲しいと、強く想っていた。
それがどうしてか、どんなに考えても分からなかったが。
は夢遊病のように兄について歩いていたが、頬に生暖かい風を感じて我に戻った。 テツヤは皆と逸れてしまったらしく、二人はちょうど会場の入り口の屋根の上あたり、テラスのような場所に出ていた。
そこには、ついさっきまでコートにいた、ずっと目で追っていた黄瀬が、手摺りに肘をついて佇んでいた。
「黄瀬くん」
テツヤが声を掛けると、黄瀬は目を見開いた。
それもそのはず、このIH開催地は自分達の住んでいる場所からかなり離れた地。 観戦にしたって、かんたんに来られるような場所ではない。 黄瀬と青峰の試合を観ている只中にこうして会うなんてでさえ驚いたのだから、 来ている事も知らなかった黄瀬にとっては、それ以上だろう。
「どうも」
「黒子っちとっち?!!なんでここに?!!」
「…はぐれました」
「は?!」
濃いブルーの空と、脱脂綿をぎゅっと圧縮させたような雲。 じわじわと蝉がなき、今が夏である事を主張している。 きっと今日みたいな日をレジャー日和というのだろう。 キャンプや海へ行くのに最適な日。
だというのに、の表情は曇っている。
他に何も考えられなくなる程にの頭の中を占領している黄瀬が目の前にいるというのに、 何を言っていいか分からない。何か声を掛けたいのに。勝って、欲しいのに。
「まさか観に来てるとは思わなかったっス」
「昨日まで近くで合宿だったので」
「ちぇー、応援しに来てくれたんじゃないんスか?」
「違います」
「ヒドッ!!」
をおいて会話はぽんぽんと進んでいく。 も何か言おうと、口を開いては閉じ開いては閉じを数回繰り替えしたが、結局きゅっと結んだ。
青峰という天才との、一度として勝った事のない、黄瀬がバスケをやるきっかけになったひととの、 大切なこの試合の只中に、何を言うというのだ。
「…じゃ、ちなみに、青峰っちと俺…、勝つとしたらどっちだと思うっスか?」
「…わかりません」
「えー…」
「ただ勝負は諦めなければ何が起こるかわからないし、二人とも諦めることはないと思います。 …だから、どっちが勝ってもおかしくないと思います」
普通に会話が出来る兄が、少し羨ましかった。 その言葉達はテツヤの本音であり、そしてきっと、黄瀬のエネルギーに変わる。
自分には無理だな。
少し寂しい気持ちになった時、今まで抱えていたモヤモヤとした気持ちが何だったのか、 はようやく気付いた。 つかえていた何かが胸にすとんと落ちるように納得がいった。
嗚呼、そうか、私は―――。
「…ふーん。じゃあせいぜい、がんばるっスわ」
「…………」
「なんスか?」
「いえ、てっきり 『絶対勝つっス』 とか言うと思ってました」
「なんスかそれ?!…そりゃもちろん、そのつもりなんスけど…」
もうすぐ後半戦が始まる。
黄瀬はこの時間にテツヤと会って、良い意味での気晴らしになっただろう。 その役目が自分でないのがやはり少し悲しいけれど、黄瀬にとって良かったのなら、それでいいと思った。
「正直自分でもわかんないス。 中学の時は勝つ試合が当たり前だったけど…、 勝てるかどうかわからない今の方が、気持ちイイんス」
黄瀬が試合 へ戻る為に、ゆっくりと歩き始める。
後半は前半よりも厳しい戦いになる事は目に見えている。 そこへ向かう黄瀬を励ますように、風が優しく撫でていく。 ゆるくなびく蜂蜜色の髪の毛がさわさわと揺れ、強い日差しに反射してキラキラと輝いた。 それは金糸のようで、場違いだと分かりながらも、そのふわふわと柔らかい感触に触れてみたいと、そう思った次の時。
目も合わす事なくの横を通り過ぎるのだろうと思っていた黄瀬のその髪が、の頬に触れた。
「だけど…」
小さな小さな声だというのに、黄瀬の声はの体を伝うように響く。
少しの間の後、自分が今どうなっているのかを理解し、は軽いパニックに陥った。
「お願い、ちょっとだけエネルギー補給させて」
頭をの肩にもたれさせ、シフォン生地で作ったストールをふわりとかけるように、 黄瀬はその腕にを抱え込んでいた。
視界に入った兄のムっとしたような表情で我に返り、つま先から頭の天辺までが熱くなっているのを感じたが、 それを振りほどく事なんてできるはずない。
「…エネルギー補給には、レモンのはちみつ漬けとかのほうが、良いと思うよ」
「ううん、コッチのほうが、絶対イイ」
黄瀬が一言喋る毎に、直接その声が身体に響く。
男に抱かれて顔を真っ赤に染める妹を見て、兄はどう思っているのだろうか。 想像すると、いたたまれない。
ぎゅっと目を閉じようとした時、自分にしか聞こえないような、 もしかしたらにも聞こえなくても良いのではないかと思えるほどに小さく気弱そうな黄瀬の声が、 内耳に入り込む。
「勝ったらさ、オレと、付き合ってくれる?」
軽い眩暈をおぼえた。
初めて聞いたその言葉。
“好き” とは、幾度となく言われてきたけれど、同じようで、全く違う。
「…っと!ジョーダンっス!いつもの、ね。それに…」
優しい拘束をパっとほどき、降参、というように黄瀬は両手を挙げた。いつもの、の返事を遮る為のもの。
けれど今日はいつもと違う。 の気持ちが、今までとは、全然違う。 は自分の気持ちを、分かってしまったから。
黄瀬はそのまま喋り続けていたけれど、今度はがそれを遮って、いいよ、とだけ、応えた。
「そんなのなくったって勝っ、え、いいよ、って、え?」
の応えに面食らっている黄瀬を見て、今度はが落ち着く番だった。 目を白黒させながら狼狽えるその姿に、は今日初めての笑みをみせた。
その笑顔は黄瀬がを意識するきっかけになった時と同じもので、それが今、自分に向けられている。 まだ何かしらの実感らしいものはないが、何か熱いものが黄瀬の胸にじんわりと、笑いとともにこみ上げてきた。
「は、ははは、ははっ、こりゃ、負けらんないっスね」
チーム集合のアナウンスがかかり、三人は同時に顔を上げた。
さっきまでは黄瀬にどう声をかけていいか分からなかったけれど、今のにはできる。 あんなに難しく感じていた事が、こうも簡単に。
「黄瀬くん」
「ん?」
「応援してる」
「…ん。ありがと、いってくるっス」
兄と一緒に観覧席に戻ると、買出しに出ていた1年全員から非難の嵐をくらった。 けれどテツヤは 「すみません」 と一言だけ返し、その理由を口にする事はなかった。
は前半と同じようにビデオカメラをまわし、スコアノートを開く。 その表情が前半の時と全く違う事に気付いているのは、きっとテツヤ一人だろう。
お気に入りの、人気者のネズミがぶら下がるボールペンを握り締め、コートに目を落とす。
後半戦の開始を知らせる、笛の音が鳴った。
***
後半戦、黄瀬は青峰の模倣 を完成させ、
前半以上に激しい戦いになった。
青峰と互角以上にも見えた黄瀬だったが、結果は、桐皇の勝利に終わった。
誠凛との練習試合に負けた時、黄瀬が見せた涙。 それは自分が泣いている事に驚いてもいるようだった。けれど、今度は違う。
悔しくて、悔しくて、悔しくて。
“この試合に勝ったら付き合う” という、10分間のインターバルにした約束の事は関係ない。 そんな事は黄瀬の頭にも、の頭にも、今は微塵もありはしなかった。
今までになく本気で、今までしてこなかった努力もして、 初めて、全力以上を出し切って、それでも青峰には届かなかった。
試合の負担が激しくて自分で立つ事すらままならず、キャプテンの笠松に支えられながら、 黄瀬は隠そうともせずに落涙していた。
は声を出す事が出来なかった。
スコアノートを乗せている膝、ボールペンを持つ手、全身が震え、思わず嗚咽が洩れそうになる口を両手を覆った。
飾る事なく悔しさを全面に出して涙を流し続ける黄瀬と同じように、も涙を止められなかった。
そんなに気付いて、何も言わずに背中をさすってくれる兄の手が、とても温かかった。
IH予選が始まり、新協学園戦、実善高校戦、金賀高校戦、明常高校戦と白稜高校戦を終え、準決勝へ進出を決めた。
やはり誠凛は強い。
油断などしていないが、皆どこか期待があったように思う。 雲を掴むような感覚だったそれが、雲の感触が少しづつ手に伝わってくるような感じ。 もしかしたら、もしかしたら。
けれどそこからは今までと明らかに違った。 それが、全国クラス。 古武術を取り入れた独自のスタイルをもつ正邦高校戦に辛勝、同日の連戦で、本当に苦しかった秀徳高校戦。 そして、決勝リーグへ。
決勝リーグ初戦、桐皇学園にダブルスコアで負け、残りも、全て ――― 。
あれだけ頑張っても手に入らなかった全国への切符。 懸命に励んでもどこか気持ちが入らずにいた。 そんな誠凛メンバーに掲げられたのが、ウィンターカップという新たな目標だった。
この誠凛バスケ部を作った木吉の復帰も皆のモチベーションを上げただろう。
新たな目標に気持ちを切り替え、この夏、WCへ向けての合宿が行われた。
秀徳とまさかの遭遇をした合宿も必死に乗り越え、その最終日。 この合宿が行われたのはIH開催都市。 元々その為にこの地を選んだのかどうかは定かではないけれど、 誠凛メンバーはIH会場へ足を運ぶ事となった。
今日の試合は、海常対桐皇。
黄瀬を見るのは、久々だった。
IH予選の秀徳戦の帰り、雨宿りと休憩で入ったお好み焼き屋で偶然黄瀬と鉢合わせたけれど、 席が離れていた事もあり、会話らしい会話は交わしていない。
帰りに、少し寂しそうな笑顔で、「もうカッコ悪いところは見せないっスよ」 と、言われただけだ。 そして黄瀬は、の言葉も聞かずに去ってしまった。
中学時代、いくら1on1で青峰に負けてもいつもどこか自信が滲んでいた。 そんな黄瀬の、弱々しい表情。 もしかしたら店内での席も、意図的に離れたのかも知れない。 今までだったら、強引にでもの隣に陣取っていただろうから。
それから、黄瀬の事が頭から離れない。
正確には、練習試合のあの日からずっと気になっていたのだが、それよりも、もっと。
「…ふへー!!ノド乾いた!!」
「なんだよコガ、いきなり」
「だってなんかキンチョー感すげーしさー、オレらすげー奴らとやってたんだなーみたいな」
「ほぼマグレ勝ちと惨敗だけどな」
海常高校 対 桐皇学園戦の幕は切って落とされ、既に第2Qが終了した。 試合のちょうど真ん中の、10分のインターバル。
喉が渇いたという小金井を日向は軽くあしらったが、えてして的を射ている。 その会場内の熱気は、夏だから、というだけでは決してない。
IHなだけあり、両校ともスタメン全員レベルが高い。 けれど会場にいる誰しもが注目しているのはやはり青峰と黄瀬で、 二人のプレイは一瞬たりとも目が離せず、観ている者の呼吸すら忘れさせた。
「確かに飲み物ほしいわね」
カントクの一言への兄テツヤが 「なんか買ってきましょうか?」 と、ぽろりと聞くと、 全員からドリンクのリクエストが殺到した。 結局1年全員で買出しへ行く事となりも一緒に席を立ったが、ほぼ無意識の状態で、 ただテツヤの後に付いて行っただけだった。
小さい頃からのクセのようなもので、何も考えていなくても体はテツヤの後を追う。 否、本当は何も考えていない訳ではない。 頭がいっぱいで、他の事が考えられなくなっていた。
試合中、はビデオをまわし、スコアもつけてはいたが、その内容も全く頭に入って来なかった。
目は、黄瀬ばかりを追っていた。
青峰と対峙する黄瀬は、今までに見た事のない目をしていた。 誠凛との練習試合の時に火神へ向けたそれともまた違う。 恐怖すら覚えそうな、ピリピリとした真剣さ。
今まで一回も勝った事のない、もしかしたら勝てなくて良いとさえ思っていたかもしれない青峰に、 黄瀬が本気で勝とうとしている事が痛い程に伝わってきた。
黄瀬くんに、勝って欲しい。
青峰も黄瀬も、どちらも仲間だった。
でもは今、黄瀬に勝って欲しいと、強く想っていた。
それがどうしてか、どんなに考えても分からなかったが。
は夢遊病のように兄について歩いていたが、頬に生暖かい風を感じて我に戻った。 テツヤは皆と逸れてしまったらしく、二人はちょうど会場の入り口の屋根の上あたり、テラスのような場所に出ていた。
そこには、ついさっきまでコートにいた、ずっと目で追っていた黄瀬が、手摺りに肘をついて佇んでいた。
「黄瀬くん」
テツヤが声を掛けると、黄瀬は目を見開いた。
それもそのはず、このIH開催地は自分達の住んでいる場所からかなり離れた地。 観戦にしたって、かんたんに来られるような場所ではない。 黄瀬と青峰の試合を観ている只中にこうして会うなんてでさえ驚いたのだから、 来ている事も知らなかった黄瀬にとっては、それ以上だろう。
「どうも」
「黒子っちとっち?!!なんでここに?!!」
「…はぐれました」
「は?!」
濃いブルーの空と、脱脂綿をぎゅっと圧縮させたような雲。 じわじわと蝉がなき、今が夏である事を主張している。 きっと今日みたいな日をレジャー日和というのだろう。 キャンプや海へ行くのに最適な日。
だというのに、の表情は曇っている。
他に何も考えられなくなる程にの頭の中を占領している黄瀬が目の前にいるというのに、 何を言っていいか分からない。何か声を掛けたいのに。勝って、欲しいのに。
「まさか観に来てるとは思わなかったっス」
「昨日まで近くで合宿だったので」
「ちぇー、応援しに来てくれたんじゃないんスか?」
「違います」
「ヒドッ!!」
をおいて会話はぽんぽんと進んでいく。 も何か言おうと、口を開いては閉じ開いては閉じを数回繰り替えしたが、結局きゅっと結んだ。
青峰という天才との、一度として勝った事のない、黄瀬がバスケをやるきっかけになったひととの、 大切なこの試合の只中に、何を言うというのだ。
「…じゃ、ちなみに、青峰っちと俺…、勝つとしたらどっちだと思うっスか?」
「…わかりません」
「えー…」
「ただ勝負は諦めなければ何が起こるかわからないし、二人とも諦めることはないと思います。 …だから、どっちが勝ってもおかしくないと思います」
普通に会話が出来る兄が、少し羨ましかった。 その言葉達はテツヤの本音であり、そしてきっと、黄瀬のエネルギーに変わる。
自分には無理だな。
少し寂しい気持ちになった時、今まで抱えていたモヤモヤとした気持ちが何だったのか、 はようやく気付いた。 つかえていた何かが胸にすとんと落ちるように納得がいった。
嗚呼、そうか、私は―――。
「…ふーん。じゃあせいぜい、がんばるっスわ」
「…………」
「なんスか?」
「いえ、てっきり 『絶対勝つっス』 とか言うと思ってました」
「なんスかそれ?!…そりゃもちろん、そのつもりなんスけど…」
もうすぐ後半戦が始まる。
黄瀬はこの時間にテツヤと会って、良い意味での気晴らしになっただろう。 その役目が自分でないのがやはり少し悲しいけれど、黄瀬にとって良かったのなら、それでいいと思った。
「正直自分でもわかんないス。 中学の時は勝つ試合が当たり前だったけど…、 勝てるかどうかわからない今の方が、気持ちイイんス」
黄瀬が
後半は前半よりも厳しい戦いになる事は目に見えている。 そこへ向かう黄瀬を励ますように、風が優しく撫でていく。 ゆるくなびく蜂蜜色の髪の毛がさわさわと揺れ、強い日差しに反射してキラキラと輝いた。 それは金糸のようで、場違いだと分かりながらも、そのふわふわと柔らかい感触に触れてみたいと、そう思った次の時。
目も合わす事なくの横を通り過ぎるのだろうと思っていた黄瀬のその髪が、の頬に触れた。
「だけど…」
小さな小さな声だというのに、黄瀬の声はの体を伝うように響く。
少しの間の後、自分が今どうなっているのかを理解し、は軽いパニックに陥った。
「お願い、ちょっとだけエネルギー補給させて」
頭をの肩にもたれさせ、シフォン生地で作ったストールをふわりとかけるように、 黄瀬はその腕にを抱え込んでいた。
視界に入った兄のムっとしたような表情で我に返り、つま先から頭の天辺までが熱くなっているのを感じたが、 それを振りほどく事なんてできるはずない。
「…エネルギー補給には、レモンのはちみつ漬けとかのほうが、良いと思うよ」
「ううん、コッチのほうが、絶対イイ」
黄瀬が一言喋る毎に、直接その声が身体に響く。
男に抱かれて顔を真っ赤に染める妹を見て、兄はどう思っているのだろうか。 想像すると、いたたまれない。
ぎゅっと目を閉じようとした時、自分にしか聞こえないような、 もしかしたらにも聞こえなくても良いのではないかと思えるほどに小さく気弱そうな黄瀬の声が、 内耳に入り込む。
「勝ったらさ、オレと、付き合ってくれる?」
軽い眩暈をおぼえた。
初めて聞いたその言葉。
“好き” とは、幾度となく言われてきたけれど、同じようで、全く違う。
「…っと!ジョーダンっス!いつもの、ね。それに…」
優しい拘束をパっとほどき、降参、というように黄瀬は両手を挙げた。いつもの、の返事を遮る為のもの。
けれど今日はいつもと違う。 の気持ちが、今までとは、全然違う。 は自分の気持ちを、分かってしまったから。
黄瀬はそのまま喋り続けていたけれど、今度はがそれを遮って、いいよ、とだけ、応えた。
「そんなのなくったって勝っ、え、いいよ、って、え?」
の応えに面食らっている黄瀬を見て、今度はが落ち着く番だった。 目を白黒させながら狼狽えるその姿に、は今日初めての笑みをみせた。
その笑顔は黄瀬がを意識するきっかけになった時と同じもので、それが今、自分に向けられている。 まだ何かしらの実感らしいものはないが、何か熱いものが黄瀬の胸にじんわりと、笑いとともにこみ上げてきた。
「は、ははは、ははっ、こりゃ、負けらんないっスね」
チーム集合のアナウンスがかかり、三人は同時に顔を上げた。
さっきまでは黄瀬にどう声をかけていいか分からなかったけれど、今のにはできる。 あんなに難しく感じていた事が、こうも簡単に。
「黄瀬くん」
「ん?」
「応援してる」
「…ん。ありがと、いってくるっス」
兄と一緒に観覧席に戻ると、買出しに出ていた1年全員から非難の嵐をくらった。 けれどテツヤは 「すみません」 と一言だけ返し、その理由を口にする事はなかった。
は前半と同じようにビデオカメラをまわし、スコアノートを開く。 その表情が前半の時と全く違う事に気付いているのは、きっとテツヤ一人だろう。
お気に入りの、人気者のネズミがぶら下がるボールペンを握り締め、コートに目を落とす。
後半戦の開始を知らせる、笛の音が鳴った。
後半戦、黄瀬は青峰の
青峰と互角以上にも見えた黄瀬だったが、結果は、桐皇の勝利に終わった。
誠凛との練習試合に負けた時、黄瀬が見せた涙。 それは自分が泣いている事に驚いてもいるようだった。けれど、今度は違う。
悔しくて、悔しくて、悔しくて。
“この試合に勝ったら付き合う” という、10分間のインターバルにした約束の事は関係ない。 そんな事は黄瀬の頭にも、の頭にも、今は微塵もありはしなかった。
今までになく本気で、今までしてこなかった努力もして、 初めて、全力以上を出し切って、それでも青峰には届かなかった。
試合の負担が激しくて自分で立つ事すらままならず、キャプテンの笠松に支えられながら、 黄瀬は隠そうともせずに落涙していた。
は声を出す事が出来なかった。
スコアノートを乗せている膝、ボールペンを持つ手、全身が震え、思わず嗚咽が洩れそうになる口を両手を覆った。
飾る事なく悔しさを全面に出して涙を流し続ける黄瀬と同じように、も涙を止められなかった。
そんなに気付いて、何も言わずに背中をさすってくれる兄の手が、とても温かかった。