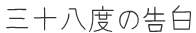じーわじーわと窓の外から蝉の声が聞こえるが、
効きすぎなくらい空調が行き届いた部屋では暑さを助長する効力はない。
薄い木目の、カーブが緩やかなモダンなローテーブルの上に置かれた、 ブラックのアイスコーヒーと牛乳たっぷりのミルクティーのグラスが、小さく汗をかいている。
今は、黄瀬の部屋にいる。
IHは洛山の優勝で幕を閉じた。
昨晩桃井から聞いた話しによると、決勝に元帝光メンバーの 『キセキの世代』 は一人も出なかったらしい。 桃井へ連絡をしたのはからだが、彼女へ連絡をしたのはその話しを聞く為でも、いつも一緒にいる青峰の事でもない。
黄瀬の、連絡先を聞く為だった。
ベッドに腰掛けて片足を上げてそれを両腕で抱え込み、膝の上に頭を乗せて首を傾ぐ黄瀬は、やはりモデルなのだなあと思う。 そのポーズひとつで雑誌の表紙のようにさまになっている。 けれど今黄瀬が見ているのはカメラのレンズではなくで、向けられた表情も、仕事用とは違う。
自嘲的な笑みを浮かべる黄瀬を、は真っ直ぐ見つめた。
「結局、まーたカッコ悪いトコ、見せちゃったっスねぇ」
黄瀬の言うそれは、IHの海常と桐皇の試合の事。 青峰と対峙して、彼が負けた時の事だ。
その時から、の頭にはずっと黄瀬の存在があり、いなくなる事がなかった。
ずっと、無性に、黄瀬に逢いたかった。
中学の時は部活で毎日顔を合わせていたけれど、高校に入ってからは数える程しか会っていなかったのに、 それが気になる事も、気にする事もなかったのに。 なのにどうしても黄瀬と話しがしたくて、昨晩とうとう桃井に黄瀬の連絡先を聞き、そのまま電話のボタンを押した。
ドキドキと胸が高鳴るのを感じながら待った5コール。 電話に出た黄瀬に近いうちに会いたいと伝えると、彼は 『じゃあ、明日』 と言った。
まさかこんなに直近で会えるとは思っていなかったけれど、誠凛もちょうど部活がオフの日。 それで黄瀬の指定した、彼の家にやってきた。
「カッコ、良かったよ?」
「へ?」
「黄瀬くん、カッコ良かった」
「…はは、ありがと」
素直に喜べない、そんな風に笑う黄瀬に、胸がぎゅうっと苦しくなった。
黄瀬は腕に両足を引き込んで、その上に頭を落とす。 今の自分の顔を、見られたくないとでも言うように。
黄瀬はの言葉を慰めか何かだと感じたのだろうか。 本当に、今までで一番カッコ良かったのに。
はあの日、黄瀬がしたように、腕を彼の首へふわりと巻きつけた。
あの時と違うのは、黄瀬からではなくが、という事と、さすがに彼のように正面からする勇気はなく、後ろから、という事。
黄瀬の体はビクリと一度反応したけれど、それをとこうとはしなかった。
「え、ええっと、、っち…?」
体を捩って振り向こうとする黄瀬に、振り向かないで欲しい、と呟くと、黄瀬の体はまた元の位置に落ち着いた。
「顔、見られたくないの。今、たぶん真っ赤だから、」
「…それは貴重っスね、オレは見たいな」
余裕あり気に言う黄瀬もまた、声が少し震えていた。
腕のなかから黄瀬の熱を感じる。 ぴたりとくっついている背中からは、彼の心音が伝わってくる。 それは、自分と同じように、早い。
既にIHは過去の事となり、雪辱をはらす為に練習に打ち込んでいるのは誠凛も海常も同じだろう。 けれど黄瀬は、あの試合をまだ完全には振り切れていないのではないかと、は感じた。 すると途端に思い出される、試合直後の、黄瀬の涙。
は心臓が絞め付けられているかのような痛苦しさに耐えられず、黄瀬を抱きしめた。
そう、あの日から、黄瀬に逢いたかった。
どうしても、伝えたい事があった。
「あの、今日は、黄瀬くんに、伝えたい事があって、来ました」
「、はい。」
「あの、ですね」
鼓動がいっそう早くなり、ぎゅっと握っている指先はもう感覚がない。 黄瀬が次に続く言葉を待ち、ゴクリと喉を鳴らしたのに気付く余裕すらなかった。
それを言うのはとてつもない勇気がいるらしい。 けれど言わずにいたら、気持ちがパンパンに膨れ上がって破裂してしまいそうだ。
は自分の呼吸が浅い事に気付き、すうと小さく息を吸い込んだ。
「どうやら私は、黄瀬くんが、好きになってしまったようです」
それをようやく言葉にした後、部屋に訪れたのは、静けさだった。
隣の家からチリンと風鈴の音が聞こえてくるほどに、部屋は静まりかえっている。 ドクンドクンと鳴る自分の心臓は、体のなか目一杯の大きさなのではないかと思うほど。 時間がこんなに長く感じた事は今までになかった。
言った事への返事が欲しいわけではない。
黄瀬もそうだったように、自分の気持ちを伝えたかっただけ。 それでもこの無言の状態はにとってかなり辛く、何でもいいから黄瀬に喋って欲しかった。 祈るように目を閉じた時、黄瀬が声を発する気配を感じ、ほんの少し肩から力が抜けた。
「嘘だあ」
「…嘘じゃ、ないです」
「――― あんなに、情けないところ、見たのに?」
「情けなくなんかなかった」
「オレ、負けて泣いてたよ?」
「黄瀬くんは、カッコよかったよ」
いくつかの問答の後、また小さな静寂が訪れる。 けれどは、腕のなかでなにかが動いている感覚に気付いた。
黄瀬の肩が、震えていた。 けれど泣いているのか、笑っているのかは分からない。
どうしたのかとが腕の力を緩めると、急に加重移動でベッドがギシリと鳴くのが聞こえ、 次の瞬間、黄瀬が振り返り、今度はがその腕におさまっていた。
急な展開に頭がついていかない。
目の前は彼のシャツしか見えない。
「うはっ」
「…黄瀬くん?」
「うははははっ」
「…変な笑い方…」
「うははははっ、だって、仕方ない、これは、仕方ない」
どうやら黄瀬は笑っていたようで、堪えきれずに声をあげた。
IH最後のあの日、自分の腕のなかにを引き込んだけれど、こんなに温かかっただろうか。 あの時はそんな余裕もなかったのかもしれない。
ひとの体温は、こんなにも温かくて、優しかったんだ。
「黄瀬くん、もしかして、喜んでる?」
「ずっとずっと好きだったオンナノコに好きって言われて、嬉しくないオトコはいないっスよ」
一通り笑って落ち着いてきたのか、ずっと揺れていた黄瀬の肩がゆっくりとした呼吸のそれに変わり、 同時に、更に力強くを引き寄せる。
ずっとずっと欲しかったものが、今自分の手の中にある。
黄瀬は確かめるようにの背を撫でた。
中学の時からずっと好きで、何度も想いを伝えて来た。 良い返事は見込めず、小さなプライドからずっと返事は聞こうとしてこなかった。
中学の頃は自分に絶対的な自信があった。 何でもソツなくこなせた。
バスケに出会い、何度やっても青峰には勝てなかったけれど、一度も悔しいとは想わなかった。 全力じゃなかった。 憧れられる唯一の存在である青峰に勝ってしまうのが怖かったから。
けれど、それは驕りだった。
練習試合で誠凛に負け、それからプライドも捨てて全力で練習してきた。
それでも、勝てなかった。
悔しくて、情けなかった。
だというのに、そんな自分を、はカッコいいと言ってくれた。
そんな自分が、好きだと、言ってくれた。
自信に満ち溢れていたあの頃ではなく、負けて泣いて、情けない今の自分を。
あの日から女々しくもずるずると引きずっていた何かがふっきれた気がした。
ありがとう、ありがとう、心のなかでに言う。けれど言葉に出すのは。
「好きっスよ。っち、大好き」
もう一度訪れた静寂はもう嫌なものではなかった。もうからの返事を遮る必要もない。
頬に触れるの髪の毛が柔らかくて気持ちいい。 緊張のせいか恥じらいのせいか、少し高いの体温が愛おしい。
黄瀬はもう一度を自分のほうへ引き込んで、その感触を確かめるためにそっと目を閉じた。
薄い木目の、カーブが緩やかなモダンなローテーブルの上に置かれた、 ブラックのアイスコーヒーと牛乳たっぷりのミルクティーのグラスが、小さく汗をかいている。
今は、黄瀬の部屋にいる。
IHは洛山の優勝で幕を閉じた。
昨晩桃井から聞いた話しによると、決勝に元帝光メンバーの 『キセキの世代』 は一人も出なかったらしい。 桃井へ連絡をしたのはからだが、彼女へ連絡をしたのはその話しを聞く為でも、いつも一緒にいる青峰の事でもない。
黄瀬の、連絡先を聞く為だった。
ベッドに腰掛けて片足を上げてそれを両腕で抱え込み、膝の上に頭を乗せて首を傾ぐ黄瀬は、やはりモデルなのだなあと思う。 そのポーズひとつで雑誌の表紙のようにさまになっている。 けれど今黄瀬が見ているのはカメラのレンズではなくで、向けられた表情も、仕事用とは違う。
自嘲的な笑みを浮かべる黄瀬を、は真っ直ぐ見つめた。
「結局、まーたカッコ悪いトコ、見せちゃったっスねぇ」
黄瀬の言うそれは、IHの海常と桐皇の試合の事。 青峰と対峙して、彼が負けた時の事だ。
その時から、の頭にはずっと黄瀬の存在があり、いなくなる事がなかった。
ずっと、無性に、黄瀬に逢いたかった。
中学の時は部活で毎日顔を合わせていたけれど、高校に入ってからは数える程しか会っていなかったのに、 それが気になる事も、気にする事もなかったのに。 なのにどうしても黄瀬と話しがしたくて、昨晩とうとう桃井に黄瀬の連絡先を聞き、そのまま電話のボタンを押した。
ドキドキと胸が高鳴るのを感じながら待った5コール。 電話に出た黄瀬に近いうちに会いたいと伝えると、彼は 『じゃあ、明日』 と言った。
まさかこんなに直近で会えるとは思っていなかったけれど、誠凛もちょうど部活がオフの日。 それで黄瀬の指定した、彼の家にやってきた。
「カッコ、良かったよ?」
「へ?」
「黄瀬くん、カッコ良かった」
「…はは、ありがと」
素直に喜べない、そんな風に笑う黄瀬に、胸がぎゅうっと苦しくなった。
黄瀬は腕に両足を引き込んで、その上に頭を落とす。 今の自分の顔を、見られたくないとでも言うように。
黄瀬はの言葉を慰めか何かだと感じたのだろうか。 本当に、今までで一番カッコ良かったのに。
はあの日、黄瀬がしたように、腕を彼の首へふわりと巻きつけた。
あの時と違うのは、黄瀬からではなくが、という事と、さすがに彼のように正面からする勇気はなく、後ろから、という事。
黄瀬の体はビクリと一度反応したけれど、それをとこうとはしなかった。
「え、ええっと、、っち…?」
体を捩って振り向こうとする黄瀬に、振り向かないで欲しい、と呟くと、黄瀬の体はまた元の位置に落ち着いた。
「顔、見られたくないの。今、たぶん真っ赤だから、」
「…それは貴重っスね、オレは見たいな」
余裕あり気に言う黄瀬もまた、声が少し震えていた。
腕のなかから黄瀬の熱を感じる。 ぴたりとくっついている背中からは、彼の心音が伝わってくる。 それは、自分と同じように、早い。
既にIHは過去の事となり、雪辱をはらす為に練習に打ち込んでいるのは誠凛も海常も同じだろう。 けれど黄瀬は、あの試合をまだ完全には振り切れていないのではないかと、は感じた。 すると途端に思い出される、試合直後の、黄瀬の涙。
は心臓が絞め付けられているかのような痛苦しさに耐えられず、黄瀬を抱きしめた。
そう、あの日から、黄瀬に逢いたかった。
どうしても、伝えたい事があった。
「あの、今日は、黄瀬くんに、伝えたい事があって、来ました」
「、はい。」
「あの、ですね」
鼓動がいっそう早くなり、ぎゅっと握っている指先はもう感覚がない。 黄瀬が次に続く言葉を待ち、ゴクリと喉を鳴らしたのに気付く余裕すらなかった。
それを言うのはとてつもない勇気がいるらしい。 けれど言わずにいたら、気持ちがパンパンに膨れ上がって破裂してしまいそうだ。
は自分の呼吸が浅い事に気付き、すうと小さく息を吸い込んだ。
「どうやら私は、黄瀬くんが、好きになってしまったようです」
それをようやく言葉にした後、部屋に訪れたのは、静けさだった。
隣の家からチリンと風鈴の音が聞こえてくるほどに、部屋は静まりかえっている。 ドクンドクンと鳴る自分の心臓は、体のなか目一杯の大きさなのではないかと思うほど。 時間がこんなに長く感じた事は今までになかった。
言った事への返事が欲しいわけではない。
黄瀬もそうだったように、自分の気持ちを伝えたかっただけ。 それでもこの無言の状態はにとってかなり辛く、何でもいいから黄瀬に喋って欲しかった。 祈るように目を閉じた時、黄瀬が声を発する気配を感じ、ほんの少し肩から力が抜けた。
「嘘だあ」
「…嘘じゃ、ないです」
「――― あんなに、情けないところ、見たのに?」
「情けなくなんかなかった」
「オレ、負けて泣いてたよ?」
「黄瀬くんは、カッコよかったよ」
いくつかの問答の後、また小さな静寂が訪れる。 けれどは、腕のなかでなにかが動いている感覚に気付いた。
黄瀬の肩が、震えていた。 けれど泣いているのか、笑っているのかは分からない。
どうしたのかとが腕の力を緩めると、急に加重移動でベッドがギシリと鳴くのが聞こえ、 次の瞬間、黄瀬が振り返り、今度はがその腕におさまっていた。
急な展開に頭がついていかない。
目の前は彼のシャツしか見えない。
「うはっ」
「…黄瀬くん?」
「うははははっ」
「…変な笑い方…」
「うははははっ、だって、仕方ない、これは、仕方ない」
どうやら黄瀬は笑っていたようで、堪えきれずに声をあげた。
IH最後のあの日、自分の腕のなかにを引き込んだけれど、こんなに温かかっただろうか。 あの時はそんな余裕もなかったのかもしれない。
ひとの体温は、こんなにも温かくて、優しかったんだ。
「黄瀬くん、もしかして、喜んでる?」
「ずっとずっと好きだったオンナノコに好きって言われて、嬉しくないオトコはいないっスよ」
一通り笑って落ち着いてきたのか、ずっと揺れていた黄瀬の肩がゆっくりとした呼吸のそれに変わり、 同時に、更に力強くを引き寄せる。
ずっとずっと欲しかったものが、今自分の手の中にある。
黄瀬は確かめるようにの背を撫でた。
中学の時からずっと好きで、何度も想いを伝えて来た。 良い返事は見込めず、小さなプライドからずっと返事は聞こうとしてこなかった。
中学の頃は自分に絶対的な自信があった。 何でもソツなくこなせた。
バスケに出会い、何度やっても青峰には勝てなかったけれど、一度も悔しいとは想わなかった。 全力じゃなかった。 憧れられる唯一の存在である青峰に勝ってしまうのが怖かったから。
けれど、それは驕りだった。
練習試合で誠凛に負け、それからプライドも捨てて全力で練習してきた。
それでも、勝てなかった。
悔しくて、情けなかった。
だというのに、そんな自分を、はカッコいいと言ってくれた。
そんな自分が、好きだと、言ってくれた。
自信に満ち溢れていたあの頃ではなく、負けて泣いて、情けない今の自分を。
あの日から女々しくもずるずると引きずっていた何かがふっきれた気がした。
ありがとう、ありがとう、心のなかでに言う。けれど言葉に出すのは。
「好きっスよ。っち、大好き」
もう一度訪れた静寂はもう嫌なものではなかった。もうからの返事を遮る必要もない。
頬に触れるの髪の毛が柔らかくて気持ちいい。 緊張のせいか恥じらいのせいか、少し高いの体温が愛おしい。
黄瀬はもう一度を自分のほうへ引き込んで、その感触を確かめるためにそっと目を閉じた。