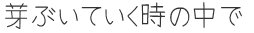中学を卒業し、は双子の兄と同じ誠凛高校へ入学した。
そして部活も同じく、バスケットボール部へ。
誠凛は昨年できたばかりの新設校。 だけれど去年バスケ部はIH予選の決勝リーグまで進んでいる。 全国を本気で目指しているという事もあり、本入部には “特殊なテスト” があるのだが、 マネージャーは大歓迎(語尾にハート)というカントクの言葉でそれは免除され、はとてもとてもほっとした。
本入部を認められ、もともと中学でもマネージャーをやっていたという事、 そして厳しくも優しいカントクや先輩達にも支えられ、部にはすぐ馴染んでいけた。
そんな時だった。
カントクが海常高校 ――― 今年、『キセキの世代』 のひとり、黄瀬涼太を獲得した高校と、練習試合を組んだのは。
はドキリとした。
黄瀬と会うのは中学卒業以来だ。 幾度となく、卒業式にも、自分なんかが好きだと言った彼と会うのは。
試合が決まった日、黄瀬は誠凛高校に来たという。 は委員会で部活に遅れてしまったせいで、 おかげでか、顔を合わさずに済んだが、試合当日にはそうもいかない。
出来ればこのまま会わずにいられたらいいのにとも思うが、それが不可能だという事もわかっている。 自分がバスケ部に所属し、黄瀬もバスケを続けている限り、遅かれ早かれ会う事になると。
決して、黄瀬が嫌いな訳じゃない。
ただ、苦手だ。
いつも誰かの後ろにいるような目立たないタイプのと、対極にいるようなひと。 華やかな彼が、自分のどこを好きになったのか分からない。 それに、きっぱりとフった訳ではないが、 好きだと言ってくれるのに良い返事を一度もしていないまま会うのは、なんだかとっても気まずい。
綺麗に晴れた春の空に似合わず、そんな事が頭にどんよりと巡る。
一年にとっては高校初となる練習試合に向かっているというのに、 冴えない顔をしているに幾人かが声を掛けたが、もちろん気が晴れる事もなく。
足は重く、いつの間にか列の最後尾まで下がっている。 けれど何をどうしても海常高校との距離は縮まっていき、とうとう辿り着いてしまった。
「どもっス、今日は皆さんよろしくっス」
絶対に無理だと分かってはいたけれど、黄瀬と顔を合わせたくないという願いは海常に足を踏み入れた途端に砕け散った。
広いんでお迎えに来ました、と人懐っこい笑顔を見せながら現われのは、黄瀬本人だった。
海常高校は運動部に力を入れているだけあり、見渡すだけでもグラウンドが数面、 校舎以外の体育館らしい建物もいくつも目に入る。 バスケ部専用の体育館もあるのだろう、確かに案内がないと真っ直ぐ辿り着くのは難しそうだが、 黄瀬がそれをやる必要もないのではないだろうか。
は思わず体格の良い火神大我の影に隠れた。 そんなを余所に、兄の姿を見付けたらしい黄瀬は 「黒子っち〜」 と、わざとらしい泣き顔をつくって駆けていく。
「あんなアッサリ フるから…毎晩枕を濡らしてんスよ、も〜…」
先日誠凛に来た際、黄瀬は兄のテツヤに自分のいる海常高校に来いと誘ったらしい。 誠凛なんかに居ては宝の持ち腐れだとまで言って。 けれどテツヤは、火神と組んで 『キセキの世代』 を倒すとそれを跳ね除けた。 その事を言っているのだろう。
「女の子にもフラれたことないんスよ〜?」
「…サラッとイヤミ言うのやめてもらえますか。 それに黄瀬くんに…」
「フラれてないっス」
黄瀬はに好きだと何度も言っていたが、返答は都度遮ってきた。 それと同じように、テツヤの言葉を遮る。
兄から出た自分の名前に、は全身をビクリとさせた。 半ば無意識に、更に火神の後ろへと入り込んでいく。 だというのに黄瀬の視線はテツヤからゆっくりと自分の方へ移り、盛大に慌てた。 テツヤが自分の名前を出したからだと兄に文句を言いたくなったが、 その視線はではなく、火神に向けられた。
「だから、黒子っちにあそこまで言わせるキミには、ちょっと興味あるんス。 『キセキの世代』 なんて呼び名に別にこだわりとかはないスけど…あんだけハッキリケンカ売られちゃあね」
にこやかだった黄瀬の表情が、勝負の時のそれに変わり、は俯いた。 今まで自分には決して向けられた事のない、勝負の相手―――敵に対する、それに。
そうか、黄瀬くんと、敵、なんだ。
ずっと仲間だったけれど、もう、違うんだ。
これは黄瀬だけでなく、全国を目指せば中学の時仲間だったひと達と戦う事になる。 当たり前の事でありながら、改めて認識すると心に何か靄がかかるようだった。
帝光中学校バスケ部のメンバーは全国の強豪校へそれぞれが進んだ。 これから何度もこんな想いをしなくてはならないのか、 それとも、それも慣れていき、何も感じなくなってしまうのか。
暗い気持ちで地面を見つめたままでいると 「それと」 と、黄瀬の声が降ってきては反射的に顔を上げる。
「何でっちはこんなヤツの影に隠れてんスか」
が顔を上げると不機嫌極まりない黄瀬の顔がすぐそばにあり、身体が硬直した。 不機嫌な顔でさえ綺麗だなんてズルイと、場違いな事も頭をよぎりつつ。
別の考えをしていたせいで一瞬忘れてしまっていたが、黄瀬の言葉で自分が隠れていた事を思い出した。 もうどうやっても隠れ続けるのは不可能。 観念しなくてはいけない。 顔が少し引き攣るのを感じたけれど、出来る限り笑顔を作って 「久しぶりだね」 と、声を絞り出したが、 それもカタコトっぽくなってしまった。
「この間せっかく誠凛まで行ったのに、会えなくて寂しかったっスよお」
「ああ、うん、えと…ごめんね、あの…委員会で、」
「聞いたっス。でもいいんスよ、今日会えたし」
にこぉと、まるで愛想を振りまく猫のような笑顔をに向けた後、黄瀬はの腕をぐいと掴んで火神の後ろから引っ張り出し、そのまま引き寄せた。
そして、不機嫌というより “睨む” といったほうが正しいキツイ視線を火神に向ける。
「オレも人間できてないんで…悪いけど、本気でツブすっスよ」
バスケ以外は何かと疎い火神は、黄瀬の言葉をただ試合への宣戦布告と受け取り、 好戦的に 「ったりめーだ!」 と返す。 他から見れば一目瞭然だというのに。
今にも抱き締めそうな勢いでを引き寄せ、それまで彼女が隠れていた火神を威嚇するような黄瀬の態度は、 牽制以外のなにものでもない。
大きいというだけでが火神の影に隠れたせいで、黄瀬に物凄い勢いで睨まれた彼を哀れに思いながらも、 その張本人が気付いていない事を皆救いに思った。
黄瀬は他のひとにも “オレの女に手を出すなオーラ” を垂れ流しながら、の腕をひいてぐんぐんと体育館へ進んでいく。
本当はと付き合っている訳でもないのだから、それはお門違いだが、 黄瀬からしたらと同じ高校にいるというだけで十分嫉妬に値したのだろう。
「っち、オレ、今日勝つから。オレの勇姿に惚れてね」
耳元でそう囁かれ、は体温が上がるのを感じた。
なんてズルイ手を使うのか。 こんなに格好良い男の人にそんな事を言われたら照れて当然だと、頬が赤いだろう自分に言い訳をしながら。
みんなの後方に居たはずだったはいつの間にか最前へと躍り出て、 そのまま一番に海常の体育館へ乗り込んでいくはめになる。
じゃれ合うような二人を、誠凛メンバーが唖然とした表情で見守るなかを。
***
自分達が海常高校に舐められているのだという事は、練習試合用に用意された片面コートを見れば理解するに容易かった。 が、結果それは負けず嫌いなメンバーに火を着ける事となり、開始直後、火神がダンクでリングを破壊し、 全面コートでリスタートするという前代未聞の試合開始になった。
途中テツヤが頭を負傷するという事態もあったが、 終盤は点の取り合い になり、
結果は、100対98、格下だと思われていた誠凛が、勝利した。
海常の監督に見下されていたせいか、カントクのリコは120%の笑顔で海常の監督に試合後の挨拶をしていた。 そこまで顔に出す者は少なかったが、他のメンバーだって嬉しいのは同じはず。 あの、IHにも毎年出ているバスケ強豪校のレギュラーに、それも今年は 『キセキの世代』 の一人、 黄瀬を獲得した海常高校に、勝ったのだから。
だというのに、は素直に喜べずにいた。 試合終了の直後からずっと、胸が苦しいまま。
――― 試合に負けた黄瀬が、泣いていた。
いつも喜怒哀楽を目一杯表現している彼だが、それは感情とイコールではないと はずっと感じていた。 が黄瀬を苦手に想う理由のひとつでもある。 演技とまではいわないが、飄々としてる、というのに近い。
そんな彼の、涙。
黄瀬は、あれ?あれ?と、自分が何故泣いているのか理解できていない様子だった。 それは純粋な涙である事の証明でもあり、 の胸をぎゅうと締め付けた。
今までスポーツでは誰にも負けた事がなかった黄瀬が中学で青峰に出会い、バスケにのめり込んでいった。 毎日毎日青峰に挑んでは負け、それでもいつもへらりと楽しそうにしていた。 試合ですらいつもどこか全力でないように見えていた黄瀬の、敗北。
黄瀬の悔しさが伝わり、胸が痛かった。
涙を流す黄瀬に声を掛けてやる事など出来ず、は来る時とはまた違った暗い想いで、海常高校を後にした。
誠凛は昨年できたばかりの新設校。 だけれど去年バスケ部はIH予選の決勝リーグまで進んでいる。 全国を本気で目指しているという事もあり、本入部には “特殊なテスト” があるのだが、 マネージャーは大歓迎(語尾にハート)というカントクの言葉でそれは免除され、はとてもとてもほっとした。
本入部を認められ、もともと中学でもマネージャーをやっていたという事、 そして厳しくも優しいカントクや先輩達にも支えられ、部にはすぐ馴染んでいけた。
そんな時だった。
カントクが海常高校 ――― 今年、『キセキの世代』 のひとり、黄瀬涼太を獲得した高校と、練習試合を組んだのは。
はドキリとした。
黄瀬と会うのは中学卒業以来だ。 幾度となく、卒業式にも、自分なんかが好きだと言った彼と会うのは。
試合が決まった日、黄瀬は誠凛高校に来たという。 は委員会で部活に遅れてしまったせいで、 おかげでか、顔を合わさずに済んだが、試合当日にはそうもいかない。
出来ればこのまま会わずにいられたらいいのにとも思うが、それが不可能だという事もわかっている。 自分がバスケ部に所属し、黄瀬もバスケを続けている限り、遅かれ早かれ会う事になると。
決して、黄瀬が嫌いな訳じゃない。
ただ、苦手だ。
いつも誰かの後ろにいるような目立たないタイプのと、対極にいるようなひと。 華やかな彼が、自分のどこを好きになったのか分からない。 それに、きっぱりとフった訳ではないが、 好きだと言ってくれるのに良い返事を一度もしていないまま会うのは、なんだかとっても気まずい。
綺麗に晴れた春の空に似合わず、そんな事が頭にどんよりと巡る。
一年にとっては高校初となる練習試合に向かっているというのに、 冴えない顔をしているに幾人かが声を掛けたが、もちろん気が晴れる事もなく。
足は重く、いつの間にか列の最後尾まで下がっている。 けれど何をどうしても海常高校との距離は縮まっていき、とうとう辿り着いてしまった。
「どもっス、今日は皆さんよろしくっス」
絶対に無理だと分かってはいたけれど、黄瀬と顔を合わせたくないという願いは海常に足を踏み入れた途端に砕け散った。
広いんでお迎えに来ました、と人懐っこい笑顔を見せながら現われのは、黄瀬本人だった。
海常高校は運動部に力を入れているだけあり、見渡すだけでもグラウンドが数面、 校舎以外の体育館らしい建物もいくつも目に入る。 バスケ部専用の体育館もあるのだろう、確かに案内がないと真っ直ぐ辿り着くのは難しそうだが、 黄瀬がそれをやる必要もないのではないだろうか。
は思わず体格の良い火神大我の影に隠れた。 そんなを余所に、兄の姿を見付けたらしい黄瀬は 「黒子っち〜」 と、わざとらしい泣き顔をつくって駆けていく。
「あんなアッサリ フるから…毎晩枕を濡らしてんスよ、も〜…」
先日誠凛に来た際、黄瀬は兄のテツヤに自分のいる海常高校に来いと誘ったらしい。 誠凛なんかに居ては宝の持ち腐れだとまで言って。 けれどテツヤは、火神と組んで 『キセキの世代』 を倒すとそれを跳ね除けた。 その事を言っているのだろう。
「女の子にもフラれたことないんスよ〜?」
「…サラッとイヤミ言うのやめてもらえますか。 それに黄瀬くんに…」
「フラれてないっス」
黄瀬はに好きだと何度も言っていたが、返答は都度遮ってきた。 それと同じように、テツヤの言葉を遮る。
兄から出た自分の名前に、は全身をビクリとさせた。 半ば無意識に、更に火神の後ろへと入り込んでいく。 だというのに黄瀬の視線はテツヤからゆっくりと自分の方へ移り、盛大に慌てた。 テツヤが自分の名前を出したからだと兄に文句を言いたくなったが、 その視線はではなく、火神に向けられた。
「だから、黒子っちにあそこまで言わせるキミには、ちょっと興味あるんス。 『キセキの世代』 なんて呼び名に別にこだわりとかはないスけど…あんだけハッキリケンカ売られちゃあね」
にこやかだった黄瀬の表情が、勝負の時のそれに変わり、は俯いた。 今まで自分には決して向けられた事のない、勝負の相手―――敵に対する、それに。
そうか、黄瀬くんと、敵、なんだ。
ずっと仲間だったけれど、もう、違うんだ。
これは黄瀬だけでなく、全国を目指せば中学の時仲間だったひと達と戦う事になる。 当たり前の事でありながら、改めて認識すると心に何か靄がかかるようだった。
帝光中学校バスケ部のメンバーは全国の強豪校へそれぞれが進んだ。 これから何度もこんな想いをしなくてはならないのか、 それとも、それも慣れていき、何も感じなくなってしまうのか。
暗い気持ちで地面を見つめたままでいると 「それと」 と、黄瀬の声が降ってきては反射的に顔を上げる。
「何でっちはこんなヤツの影に隠れてんスか」
が顔を上げると不機嫌極まりない黄瀬の顔がすぐそばにあり、身体が硬直した。 不機嫌な顔でさえ綺麗だなんてズルイと、場違いな事も頭をよぎりつつ。
別の考えをしていたせいで一瞬忘れてしまっていたが、黄瀬の言葉で自分が隠れていた事を思い出した。 もうどうやっても隠れ続けるのは不可能。 観念しなくてはいけない。 顔が少し引き攣るのを感じたけれど、出来る限り笑顔を作って 「久しぶりだね」 と、声を絞り出したが、 それもカタコトっぽくなってしまった。
「この間せっかく誠凛まで行ったのに、会えなくて寂しかったっスよお」
「ああ、うん、えと…ごめんね、あの…委員会で、」
「聞いたっス。でもいいんスよ、今日会えたし」
にこぉと、まるで愛想を振りまく猫のような笑顔をに向けた後、黄瀬はの腕をぐいと掴んで火神の後ろから引っ張り出し、そのまま引き寄せた。
そして、不機嫌というより “睨む” といったほうが正しいキツイ視線を火神に向ける。
「オレも人間できてないんで…悪いけど、本気でツブすっスよ」
バスケ以外は何かと疎い火神は、黄瀬の言葉をただ試合への宣戦布告と受け取り、 好戦的に 「ったりめーだ!」 と返す。 他から見れば一目瞭然だというのに。
今にも抱き締めそうな勢いでを引き寄せ、それまで彼女が隠れていた火神を威嚇するような黄瀬の態度は、 牽制以外のなにものでもない。
大きいというだけでが火神の影に隠れたせいで、黄瀬に物凄い勢いで睨まれた彼を哀れに思いながらも、 その張本人が気付いていない事を皆救いに思った。
黄瀬は他のひとにも “オレの女に手を出すなオーラ” を垂れ流しながら、の腕をひいてぐんぐんと体育館へ進んでいく。
本当はと付き合っている訳でもないのだから、それはお門違いだが、 黄瀬からしたらと同じ高校にいるというだけで十分嫉妬に値したのだろう。
「っち、オレ、今日勝つから。オレの勇姿に惚れてね」
耳元でそう囁かれ、は体温が上がるのを感じた。
なんてズルイ手を使うのか。 こんなに格好良い男の人にそんな事を言われたら照れて当然だと、頬が赤いだろう自分に言い訳をしながら。
みんなの後方に居たはずだったはいつの間にか最前へと躍り出て、 そのまま一番に海常の体育館へ乗り込んでいくはめになる。
じゃれ合うような二人を、誠凛メンバーが唖然とした表情で見守るなかを。
自分達が海常高校に舐められているのだという事は、練習試合用に用意された片面コートを見れば理解するに容易かった。 が、結果それは負けず嫌いなメンバーに火を着ける事となり、開始直後、火神がダンクでリングを破壊し、 全面コートでリスタートするという前代未聞の試合開始になった。
途中テツヤが頭を負傷するという事態もあったが、 終盤は
海常の監督に見下されていたせいか、カントクのリコは120%の笑顔で海常の監督に試合後の挨拶をしていた。 そこまで顔に出す者は少なかったが、他のメンバーだって嬉しいのは同じはず。 あの、IHにも毎年出ているバスケ強豪校のレギュラーに、それも今年は 『キセキの世代』 の一人、 黄瀬を獲得した海常高校に、勝ったのだから。
だというのに、は素直に喜べずにいた。 試合終了の直後からずっと、胸が苦しいまま。
――― 試合に負けた黄瀬が、泣いていた。
いつも喜怒哀楽を目一杯表現している彼だが、それは感情とイコールではないと はずっと感じていた。 が黄瀬を苦手に想う理由のひとつでもある。 演技とまではいわないが、飄々としてる、というのに近い。
そんな彼の、涙。
黄瀬は、あれ?あれ?と、自分が何故泣いているのか理解できていない様子だった。 それは純粋な涙である事の証明でもあり、 の胸をぎゅうと締め付けた。
今までスポーツでは誰にも負けた事がなかった黄瀬が中学で青峰に出会い、バスケにのめり込んでいった。 毎日毎日青峰に挑んでは負け、それでもいつもへらりと楽しそうにしていた。 試合ですらいつもどこか全力でないように見えていた黄瀬の、敗北。
黄瀬の悔しさが伝わり、胸が痛かった。
涙を流す黄瀬に声を掛けてやる事など出来ず、は来る時とはまた違った暗い想いで、海常高校を後にした。