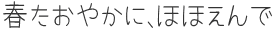スカウトを機に始めたモデルの仕事は自分に合っていると思うし、楽しい。 けれど、自分の求めているものとは何かが違った。 スポーツは好き…だけど、やったらすぐ出来てしまうからすぐに相手がいなくなる。 対戦スポーツをやっていて相手がいなくなる事程つまらないものはない。
その時求めていたものは、アツくなれる事。
もしかしたらそんなもはのないのかもしれないと半ば諦め、 くすぶっていた黄瀬が中二の春に出会ったのは、バスケ部の、青峰大輝だった。
黄瀬の通っている帝光中学校は、はからずもバスケットボール部の超強豪校。
青峰のプレーに惹かれ、青峰を追いかけるように勢いで入部し、2週間で一軍に昇格。 その頃出会ったのが、教育係になった黒子テツヤと、その双子の妹でマネージャーの、 だった。
の第一印象は、可愛いけど、なんかウスいコ。
あの黒子テツヤの双子の妹なのだから “ウスい” のは当たり前といえば当たり前。 けど、あまり似ていなかったから、初めて双子だと聞いた時は驚いた。 そしてその後に、納得した。
それは2軍の練習試合に黒子と参加し、彼のプレイを目の当たりにした少し後だったと思う。 黄瀬には彼のプレイが自分を犠牲にしたものに見えた。それは自分には到底無理な事。 けれどテツヤはただ勝利への純粋さだけで、犠牲だとかいう想いはコレっぽっちも考えておらず、 それに心底尊敬の念を抱いた。
かたちは若干違うが、妹の、に対しても、等しく。
その頃の黄瀬は、夜遅くまで1on1を挑み続けていた。 やってもやっても勝てない。 そんな経験は今までに一度もなく、あまりにも新鮮で、とても楽しかった。 青峰にいい加減にしろと文句を言われてようやく時間に気付く、そんな毎日。
その帰りに、をよく見掛けた。
部員でも残っていたのは自分達くらいなのだから、時間はかなり遅い。
は一人、体育館外の水飲み場で、ほんの少し笑みを浮かべながら洗濯をしていた。 冬場だってそう。 水は氷のように冷たいだろうに、それでも楽し気に。
きっとそれは兄のテツヤと同じ感覚なのだと感じた。
純粋にバスケが好きで、純粋に部員の支えになりたいのだという。
それに気付いた時、もうに惚れていたのだと思う。 自分にない純粋さに、ひどく惹かれた。
無意識に目はいつでもを探し、追うようになっていた。
他のひとに笑顔が向けられたのを見た時は嫉妬し、それでも小さな仕草が可愛くみえ、 時折自分に気付いて笑いかけられると、抱き締めたいという焦燥にも似た欲求に駆られた。 もしかしたら、自分に全然靡かないところも良かったのかも知れない。
はっきり言って、オンナノコなんか選り取り見取り。
だというのに言動ひとつで一喜一憂し、気付いた時には自分でも引くくらい好きになっていた。
「あー、いたいた、っちー」
中学生活最後の日、卒業式の今日。
式を終えて外に出ると、黄瀬は予想通り囲まれた。
これもモテるオトコの性。 群がる女の子達にもみくちゃにされ、花やらプレゼントや手紙やらをこれでもかと抱えさせられ、 ブレザーからセーターからワイシャツまでボタンというボタンをひん剥かれたなかでたったひとつ、 守り抜いた物。
それを渡すつもりのを女の子達の隙間から見付け、声を掛けたが…、なんと、華麗にスルー。
「ちょ!ちょっと!っち、っちってば!待って!!」
人混みをかき分けて、を追いかける。
気付かないふりをして去ろうとしたのだろうが、大きな声で名前を呼ばれて観念したのか、 は小さな溜息をつきながら振り返った。
薄い水色の空に薄桃色の桜の花びらが舞う、そに佇むは、とても可憐だ。 それは恋は盲目…という事を差し引いても。
確かに一見地味で、存在感のウスい子だけれど、がこんなに可愛い事に気付かない男達の目は節穴だと心から思う。 まあ気付かなくていいというか、気付いて欲しくもないし、 それを自分だけが知っているという優越感は堪らない。
黄瀬は口角が上がっていくのを感じながらも止められなかった。
距離を縮めると、薄桃の雨で隠れていた表情が徐々に鮮明になっていく。
なんというか、とても嫌そうだ。
「中学最後の日にそんな顔しないで欲しいんスけど…」
「黄瀬くんからは見えないかも知れないけど、黄瀬くんが置いてきた女の子達から凄い形相で睨まれてるの。」
の言葉に、乾いた笑いしか出てこなかった。 後ろは怖くて見られない。
しかし、そこまでしてでも彼女のところに来る理由があった。 今日しか出来ない事の為に。 そう、手の中にあるソレを渡す為に。
「っち、はい、これ」
「…、え」
優しい風が吹き、さわさわと桜が舞う。 そのなかで大きな目を見開くは…以下同文。 魅入ってしまいそうだった黄瀬は今はそれどころではないとブンブンと頭を振ってから の手を取り、もみくちゃにされても死守したそれを強引に持たせた。
「え、と、ボタン?」
「そうっス、ウチの制服ブレザーだけど、一応、第二ボタン」
「ありがとう。でもいらな…」
「わー!わー!わー!わー!」
大きな声を出しつつ耳に手を当てての言葉を遮る。 そしての手を両手でぎゅっと包んで握らせた。
それはただのボタン。 でも卒業式での第二ボタンというのは、特別な意味をもつ。
「もうコレはっちの。返却不可!」
「黄瀬くん、強引…」
迷惑そうなはボタンに視線を落とし、そこにあった男の人に握られた自分の手を見て赤面した。 ちょっと遅れたその反応に、思わず口元が緩んでしまう。 大丈夫。 オトコとしては認識されているらしい。 全く脈がない訳ではない。
直後、の口唇がきゅっと結ばれ、黄瀬を見上げた。
「黄瀬くん」
「うん?」
「こういうのは、彼女にあげたほうが良いと思う」
「え?そんなのいないっスよ」
「嘘、」
「嘘じゃないっス」
「だって、先月、部活がお休みの日に駅前で見掛けたよ」
「あ、ああ、」
今まで女の子にフラれた事はない。――― と、言い張る。
自慢じゃないが、これまでに告白された事は数えられない。 勿論それは多数からで、返事はYesだったり、Noだったり。
自分から好きだと言った回数は、10を越えるくらい。 でもそれはたったひとりに。 にだけ。
これだけ好きでずっと追い掛けているが、自分をどう思っているかなんて、悲しいくらいに知っている。 だから黄瀬の言葉に応えようとが口を開く度にそれを遮り、返事は聞いた事がない。
だから、フラれてはいない、と、言い張る。
フラれてはいないが全く進展しない関係に次第に焦れはじめ、 自分の気持ちを終わりにさせようと、三年に上がってからは好きだと言うのを止め、 そして告白される度に色々なコと付き合ってみた。 が言った “先月見た彼女” も然り。 モデルをしている雑誌の編集者。 いわゆる年上美人。
だけど、ダメだった。
どんなコと付き合っても、やっぱり自分の気持ちは変わらなかった。
「もう、別れた」
の顔が、怪訝そうに歪む。 そんな表情でさえ、しつこいけれど以下同文、なのだから、 自分はよっぽど重症なのだろう。
はらりと落ちてきた桜の花びらが一枚、ふわりとの髪の上に乗る。 それに触れたいという欲求を抑えきれず、手を伸ばし、目を伏せた。
やわらかい髪の毛の感触が伝わってくる。
「ヤケになって何人かと付き合ってみたんだけど…やっぱ違うんスよ。 オレが好きなのは、っちだけ」
目を閉じたのは、その表情を見たくないから。 想像通りだと、やはり凹むから。
きっと笑ってくれてなんていない。
自分の気持ちをフっ切る為に色んなひとと付き合っただなんて、の性格からすると、その子達の事を考えて、きっと悲しい顔をしているに違いない。
今はの顔を見るのが少し怖かったけれど、ずっと目を閉じている訳にもいかない。
っちが、好き。
もう一度小さく言ってから、薄っすらと目をあけた。 目に入ったははやり眉を八の字にしており、思わず自嘲の笑みを浮かべてしまう。
次に自分がとる行動も分かっている。
の口が開こうとした瞬間、それを遮る。今までもしてきたように。
「オレを好きになってくれるまで、返事は聞かないから」
そう言うと、は決まって言葉を飲み込む。 飲み込んで、くれているのだと思う 。いくらフラれてはいないと言ったところで、心は、ほんの少し、痛む。 それを気遣ってくれているのだろう。
今まで女の子にフラれた事はない。
今だって、フラれてはいない。――― と、言い張る。 だってそれを認めてしまえば、との未来は望めなくなってしまうから。 諦めるなんて、出来ないから。
精一杯の見栄で、自分の一番の笑顔をつくる。モデルだしそんなのは得意だ。
これからは別々の高校に進む。 これまでのように毎日顔を合わす事もできない。 だから尚更、情けない顔など見せられない。
そ れ じ ゃ 、ま た ね 。
背を向けてひらひらと手を振り、中学生のに別れを告げた。
中学生活の最後、第二ボタンを受け取ってもらえたのだけが良い思い出だなんて、 オレ、カッコワル。