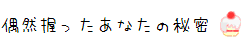は今、仕事が楽しくて仕方がない。
元々大好きな仕事なのだが、まず今は季節がいい。 冬はまだ良いとして、夏は最悪だ。 の仕事は特殊な場合を除いて屋外であり、 しかも全身を覆われているからサウナなんてもんじゃない。 灼熱だ。地獄だ。 だからこの少し肌寒いこの季節は一年で一番好きな季節でもある。
それだけではない。
の勤めるイーストトーキョーユナイテッド、通称ETUに、 彼が戻ってきたのも大きな要因だ。
10年前、ETUを出ていった、ETUに夢を見せてくれた、達海猛が。
彼がETUを出ていった時まだ学生だったは、大人達が何故そこまで彼に対して怒っているのかあまり理解出来なかったが、 寂しかったのは確かだ。 それでもETUのサポーターである事を辞めるなんて出来ず、結局は就職するまでになった。
そしては、今やETUになくてはならなくなっている。
とはいえ、彼女の存在を知っているのは、ほんの一部の人間のみだが。
そして今日の仕事もとても楽しかった。
試合はなかったのだけれど、クラブハウスで行われた地域のチビッコ達との交流イベントが行われ、 それにもかり出された。 子供達や選手達、コーチや監督、フトント陣まで勢揃いでとても楽しいイベントになった。 しかも、午後早い時間に終わり、陽が傾く前に終業。 こんな日は滅多にないが、にとって一番楽しみにしている日でもある。
は空以外何も見えない、開けたその世界で風を仰ぎながら後ろに倒れ込んだ。 所謂大の字、という格好で。
ETUのクラブハウスの屋上。
誰も上がって来る事がないだけの特別な場所。 そもそもその場所へ上がる為の梯子もついていないから、屋上でなく、ただの “屋根の上” なのかもしれない。 けれど、誰が置いていったのか、側にはいつも脚立があり、それを有り難く使わせてもらっている。
グラウンドの芝の香りをふんだんに含んだ爽やかな風が頬を撫でる。 少し汗ばんだ肌に心地良い。
仕事柄、少し肌寒い季節といえ汗をかいてしまうので、いつもこっそり選手用のシャワーを拝借している。 が、もちろん選手が全員帰ってからになるので、その間こうして屋上で過ごしているのだ。
は身体を起こしてひとつに纏めていた髪を解く。 ハラハラと自由になった髪の毛達が風に踊る。
本当に気持ちが良い。はもっと風を感じようと目を閉じたが、ガシャガシャという音にパチリと開きなおした。
すぐ側で聞こえるその音の正体が脚立だと気付くまでに時間はかからなかった。 また、それは脚立が片付けられてしまう音などではなく、誰かが上がって来る音だと分かったのもそのすぐ直後。 そして、焦りながら先ほどまで被っていた “頭部” に手をかけた瞬間だ。
上がって来たひとと、目が合ってしまった。それはもう、バッチリと。
「あ」
その声は同時にお互いから発せられた。と、屋上にやって来た、達海猛から。
それから数秒、まばたきのみの時間が流れる。 どうやっても逃れられないこの状況に、の頭は真っ白になっていた。 指先ひとつ動かせずにいたに対し達海は何事もなかったかのように脚立を上りきり、 “ヨイショ” という声とともにの隣に腰を下ろした。
「ここ風がキモチーんだよねえ」
未だ動けずにいるを横目に足を放り出して座る達海は、空を見上げながらそう言った。 言葉は確かにへ向けられているというのに、まるで独り言のように。 そう、だからから返事がなくとも関係ない。 達海の独白はそのまま続けられる。
「寝っ転がると空以外なーんも見えないし」
「昔っから全然変わんないし」
昔から、という事は、選手時代もここへ登っていたのだろうか。 達海の選手時代、はスタッフでもないただの学生のサポーターで、この建物へは出入りしていなかったので知らない。 そうか、脚立も彼が用意したもので、ずっとそのままだっただけなのかも知れない。 現実逃避か、は自分の置かれた状況を頭の隅に追いやり、そんな事を考えていた。
「しっかし、」
達海が顔をくるりとに向ける。途端に、現状を思い出す。 一気に冷や汗が噴出してくる。 目の前がぐるぐる回る。 どうしよう、どうしよう、どうしよう。
「俺に用があって来るヤツはいたけど、それ以外でこの場所に登るヤツが俺以外にいたとはなー」
気が動転しているは、達海と今ここで会った事を “なかった事にしよう” と、 もしかしたら彼もそうしてくれるかも知れないと、 およそ無理な願いを込め、手に掛けたままだった緑色を持ち上げようとした、 が、達海のチョップによりそれはボトリと音をたてて落ちた。
「それも、パッカが。」
「いや、パッカじゃないのか?だって今パッカの頭ねーもんな。 いや、なくはないか、下に落ちてっから。 つか俺が落としたから。 じゃーパッカの首から下?あ、パッカの、中のひと、か。」
そう、達海は知ってしまった。 の仕事であり、の最大の秘密を。
の仕事は一言で言えばスーツアクターというもの。
着ぐるみをきて、そのキャラクターを演じる。 高校時代ETUの試合チケットを買う為にデパートの屋上でそのバイトをしていた経験をかわれ、先代からパッカを引き継いだ。
それを知っているのは、ETUフロント陣トップである会長と、スカウティングの笠野、そして先代の三人のみ。 というのも、その先代の唯一の教えが、“パッカに中の人間などいないのだ” という事だったから。
実際はパッカの着ぐるみをが着ているのだが、それでパッカを演じるのではなく、それはパッカ自身であり、ではなく、ただ動くのにの力を借りているだけなのだ、というプロ根性。
だから “” は、ここに存在してはいけない。いるのは、パッカ。
故に知っているのは極限られた人間であり、チーム内であろうと、他に知られる事はご法度なのだ。
それが洩れたりした日にはもう、先代に顔向けも出来ない。
の背筋は冷や汗で冷たくなっていく。
固まったままのを見て、がパッカの中身だという事を、彼女は隠したがっていると達海は分かってしまったのだろう。
“ニヤリ” と、にはハッキリその効果音が聞こえた。 達海のあきらかに悪い事を考えている顔に、は頬を引きつらせた。