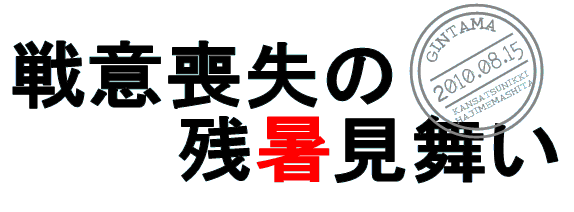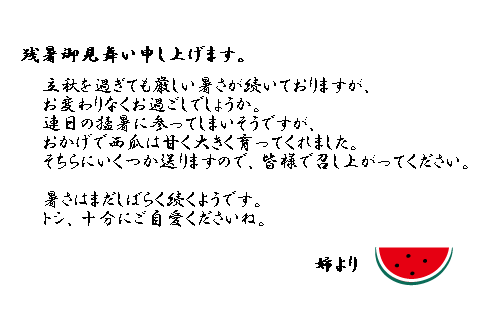
|
じりじりと照り付ける太陽と、セルリアンブルーの絵の具をべったりと塗りつけたような空、
そして、ちぎって食べられそうな程のもくもくな雲。
夏を主張しているのは開けっ放しの障子戸の間から見えるその景色だけでなく、
耳につくセミの鳴き声が 「死ね死ね死ね死ね死ね死ね」 と言っているようにも聞こえ、
この暑さに加えて更に苛々させる。
てめェらは総悟のマワシモノかと1匹1匹捻り潰してやりたくなるが、まあ、それが現実的に無理なのも分かっているし、
半ば八つ当たりなのもわかっている。
けれどこの苛つきはどうしようもなく、その、大元の原因である目の前に座る女に向かって舌打ちをした。 「で?」 「…で、とは、どういう事でしょうか…」 「なんで、お前がここに居るんだ、って聞いてんだ」 「あの、残暑見舞をお届けに…」 「そんなのは見りゃ判る!」 ダン!と思い切り座卓を叩くと目の前に居る女は肩をビクリと揺らした。 けれど怯えながらも引く様子はなく、身体を強張らせながら土方を見据える。 「…トシさんのお姉さまに頼まれて、西瓜を届けに参りました」 彼女の声は、少し震えていた。 気丈に振舞っているつもりだろうが、泣く子も黙る真選組の鬼副長に凄まれたら怖いに決まっている。 勿論土方が不機嫌なのは彼女が持って来た西瓜が嫌いだからという訳ではない。 むしろ西瓜は好きだ。 そんな事ではなく、彼のご機嫌が麗しくないのは、その西瓜を持って来た女 ――― が、真選組屯所までやって来たから、だ。 「じゃ、用が済んだなら、帰れ」 「よ、用事はまだ済んでおりません…!」 「あのなァ!俺だって暇じゃねェんだよ」 をギロリと睨みつけると、彼女は口唇をきゅっと一文字に結び、 それと同時に、麦茶が注がれたグラスについた水滴が、冷汗のようにつうと零れ落ちた。 「姉さんも何考えてんだ、ったく…」 もう何年も会っては居ないが、土方には姉が居る。 姉とその夫は昔から何かと土方の世話を焼き、今もこうして便りと一緒に物を送ってくる。 それも今まではずっとクール宅配便だので送って来ていたのにも関わらず、今回は何故か、にそれを任せたらしい。 昔、姉と今は亡き義兄が決めた許婚だった、が。 「お前とは縁を切ったはずなんだが」 許婚などという関係があったのは、田舎道場で燻っていた頃の事。 その後真選組を作り上げ、攘夷戦争が激しくなり、真選組もその渦中で忙しくなっていった頃、土方はの元に出向いてそれを白紙に戻した。 女に構っている余裕も暇もなかった。 自惚れでなく想い合っていた女性でさえ、土方は切り捨てたのだから。 それ以来と会っていないし、存在も頭の片隅に追いやり、思い出す事すらなかった。 「人の縁は…そう簡単に、切れるものではありません…」 に恋愛感情は一粒も持ち合わせていなかったが、妹のように想っていたのは確かだった。 最初は世話になっている姉夫婦を邪険にする訳にいかないから、仕方なくと会っていたのだが、彼女の特技は自分の趣味の一つだったり、 少女ながらにしっかりとしている部分にも好感をもて、当時は良くしてやっていた。 総悟に「土方さんのロリコンやろー」等と言わせてやる程度には。 その総悟と変わらない餓鬼だったが、すっかり大人の女性になって今土方の前に座っている。 「俺が最後にお前に言った事、忘れたか?」 はそれを思い出したのか、目を見開いて土方を見て、その瞳に涙を溜めた。 彼女が自分を慕っているのは感じていた。 自分もを妹として可愛いと思っていた。 だからこそ、一抹の未練すら残らぬように言って別れた。 元々一緒になるつもりは無かった、もう餓鬼のお守りをしている余裕もねェし、お前には飽きた、と。 「…トシさんに、事情があったんだと、聞きました」 「はァ?誰にだ、ッたく、何言って…、」 事情があった?確かにあった。 余計な事をに吹き込んだのは姉だろう。 けれど、を女として見た事がなかったのは確かだし、今後も見るつもりはない。 だけでなく、武装警察の副長として、恋愛だのにかまけている暇などない。 「トシさんが本当はとっても優しい事、知っています」 「………自惚れんのも、大概にしとけ」 「う、ぬぼれ…あ、あたしはただ、ただ…」 の涙の水位は少しづつ確実に上がってきている。 土方は、こんなにも酷い事を言っている男に必死になっているが、正直不思議だった。 ここまで言われて、何故帰らないのか、どうして諦めないのか。 もしかしたら、は今まで一途に自分を想っていたのか?と思うと、チリと胸が痛いけれど、だったら尚の事、諦めてもらうより他は、ない。 「わ、わたし、トシさんの許婚に戻りたいなんて図々しい事は言いません…!」 胸の前で両手をぎゅうと握り締め、必死に訴えてくる。 昔こっ酷く振られた相手に数年ぶりに会うのだから、それなりの覚悟をして来ているのだろう。 が悪いんじゃない。 自分の人生に、女は必要ないだけなんだ。 口に出して言えない分、頭の中でそう言ってやる。 「でもあたし、あたし、トシさんの事がっっ」 好きです。きっと後にはそう続く。 「俺が言った事に今も変わりはない。帰れ」 そう言って、突き放すしかない。 今は傷付いても、きっと自分より良い男が現れるはずだから。 そのほうがにとって、幸せなはずだから。 「あたし、トシさんの事、好きなんです!ずっと、ずっと…!!」 頭で考えていても、実際そう言われると胸の辺りがぐっと苦しくなる。 落ち着く為に煙草に火を着け、煙を大きく吸い込み、さっきシュミレートした言葉を思い出す。 自分もこんな事を言うのは辛い、けれど言わなければならない。 「俺が言った事に今も…――― 」 「だからトシさん!お友達からお願いします…っっ!!」 「ええェェェ?!ねるとんんんー?!!」 昔流行ったお見合い番組のように手を出して握手を求める格好のに、おもわずツッコミを入れてしまう。 これも長年ボケだらけの周りに囲まれていた性か。 急に空気の変わった二人の間に、微妙な時間が流れる。 |